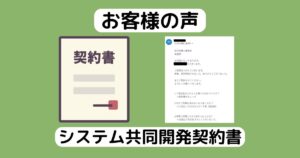ユキマサくん
ユキマサくんクライアントからAIを使った社内システムを作ってくれって頼まれたんだけど、請負契約と準委任契約とか違いがよく分からないんだよね。
契約書の作成時に気を付けるポイントと一緒に教えてくれニャいかな。



わかりました。
それでは今回は、フリーのITエンジニアの方に向けて、契約形態の違いと契約書作成の注意点について解説しますね。


なぜ請負契約と準委任契約の理解が重要なのか?
システム開発の現場では、従来の受託開発だけでなく、アジャイル開発やスクラム開発など、さまざまな開発手法が採用されています。
それに伴い、契約形態も多様化しており、従来の請負契約一辺倒から、準委任契約を採用するケースが増えてきています。
同時に、システム開発契約特有のトラブルも多発しています。
トラブル事例
弊所は契約書の作成業務を通じて、実際にフリーランスの方から以下のようなトラブルを耳にすることがあります。
- 「要件定義が曖昧なまま請負契約を結んでしまい、開発途中で仕様が大きく変更になったものの、追加費用を認めてもらえなかった」
- 「準委任契約だと思っていたのに、成果物の完成責任を求められ、追加作業を要求された」
- 「契約書の内容をよく確認せずに署名してしまい、想定以上に修正を求められた。時給換算したら大赤字だった。」
このように、両者の契約形態の違いをよく理解しないまま作業に入るとトラブルに発展してしまうことになります。
追加の作業はフリーランスにとって大きな負担となりかねません。
請負契約と準委任契約の基本的な違い
このような契約トラブルを防止するためには、システム開発契約書を作成・締結する前に、請負契約と準委任契約の基本的な違いを理解しておくことが重要です。
請負契約の特徴
請負契約は、民法第632条に規定されています。その主な特徴は以下の通りです。
仕事の完成義務がある
- 発注者の要望に沿った成果物を完成させる義務がある
- 途中経過ではなく、最終的な成果物が重要
フリーランスのITエンジニアにとって、この完成義務は重要な意味を持ちます。
例えば、Webアプリケーションの開発を請け負った場合、要件定義書に記載された全ての機能が正常に動作する状態まで作り込む必要があります。
途中で技術的な困難に直面しても、代替案を提示するなどして、最終的な完成まで責任を持つことが求められます。
契約不適合責任を負う
- 成果物に契約の内容に適合しない部分がある場合はその責任を負う
- 修補請求や損害賠償請求の対象となる
- 通知期間内であれば、発注者は代金減額請求や代替での納品など様々な請求が可能
例えば、開発したシステムにバグが発見された場合や、セキュリティ上の脆弱性が見つかった場合、あなたは無償で修正対応を求められる可能性があります。
特にセキュリティ要件については、契約書での明確な定義が重要ですので、完成品の具体的な基準を設定しておくことをお勧めします。
報酬の支払時期
- 原則として成果物の引渡し時
- 成果物が完成していない場合、報酬請求は困難
- 途中で解約された場合の報酬計算に注意が必要
請負契約では報酬は成果物の引き渡しと引き換えが原則です。
しかし契約により、中間金を先にもうらうことも問題ありません。
例えば、「要件定義完了時30%」「基本設計完了時30%」「最終納品時40%」といった形で、各プロジェクトごとの支払いを設定することで、報酬の取りっぱぐれを防ぐことができます。
準委任契約の特徴
準委任契約は、民法第656条で規定されています。主な特徴は以下の通りです。
善管注意義務
- 仕事の完成ではなく、善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務
- プロセスを重視し、適切な助言や報告が求められる
- 結果の完成を約束するものではない
請負契約と異なり、準委任契約では受任者は仕事の完成義務を負わない点が特徴です。
例えばアジャイル開発の場合は、準委任契約が適していることが多いです。
準委任契約では日々の報告や、レビューでの成果物を提示したり、プロセスの透明性を確保しながら開発を進めることができる一方、定期的な報告や記録作業が負担になることもあります。
責任の範囲
- 善管注意義務を果たしていれば、結果の成否は問われない
- 途中経過の報告や相談が重要
- 作業時間に応じた報酬が可能
例えば、新規サービスの開発で技術検証を行う場合、必ずしも期待した結果が得られるとは限りません。
その場合でも、検証を行い、結果を適切に報告していれば、きちんと契約義務を果たしたことになります。
報酬の支払時期
- 通常は月払いなど、期間に応じて支払う
- 作業時間や工数に基づく報酬計算も可能
- 中途解約時も既履行部分の報酬請求が可能
スタートアップ企業との取引や、保守運用案件では、準委任契約の体系が用いられることが多いです。
例えば、「月40時間の作業で10万円」、「月に2回クライアント先に入り、午前中3時間だけ保守メンテする」といった形で報酬を設定します。
追加の作業が発生した場合は、時間精算で対応することも可能です。
システム開発の特性から見た契約形態の選び方
フリーランスのITエンジニアとしてクライアント企業から仕事を受注する際、プロジェクトの特性に応じて適切な契約形態を選択することが重要です。
ここでは、実際の開発現場で遭遇する具体的なケースに基づいて、契約形態の選び方を解説します。
要件が明確な場合
Webアプリケーションやモバイルアプリの開発など、要件が明確に定義されているケースでは、請負契約が適していることが多くあります。
以下のようなプロジェクトでは、請負契約を選択することで、フリーのITエンジニアとしての裁量を活かした開発が可能になります。
- パッケージソフトのカスタマイズ
- 既存システムの機能追加
- 仕様書が詳細に定められている開発案件
たとえば、ECサイトの決済機能追加や、既存の社内システムへのAPI連携機能の実装など、技術要件が明確で、必要な工数の見積もりが容易なケースが該当します。
これらの案件では、エンジニアが自身の開発経験を活かして効率的に作業を進められるため、請負契約による受注が有利になります。
ただし、契約締結時には以下の点に特に注意が必要です。
- 要件定義書の内容を詳細にレビューする
- 非機能要件(性能・セキュリティなど)を明確化する
- 想定される変更範囲を事前に確認しておく
特に非機能要件については、見落としがちな部分です。
例えば、「同時接続ユーザー数100人以上」といった具体的な数値目標がある場合、それらを達成できるのか?を十分検討する必要があります。
アジャイル型開発の場合
近年のAIシステム開発の現場でもアジャイル型を採用するケースが増えています。
例えば、新規サービスの開発では、市場のフィードバックに応じて機能要件が頻繁に変更されることがあります。
このようなアジャイル型開発では、成果物の完成を約束する請負契約ではなく、準委任契約を選択することで、柔軟な開発体制を維持できます。
保守・運用契約の場合
フリーランスのITエンジニアやシステム開発会社は、新規開発だけでなく既存システムの保守・運用案件も請け負うこともあると思います。
この保守・運用フェーズでは、継続的なサービス提供が求められるため、準委任契約が選択されることが一般的です。
- 作業内容が定期的な監視・メンテナンスである
- 障害対応など予期せぬ事態への対応が多い
- 継続的な改善提案が求められる
- サービスレベルの維持が主目的である
例えば、ECサイトの保守運用を担当する場合、日次のバックアップ確認、パフォーマンスのモニタリング作業などの定常業務に加えて、突発的なシステム障害への対応が求められることがあります。
このような業務の性質上、保守・運用契約では、作業の完了を約束する請負契約ではなく、善管注意義務を基準とする準委任契約が適しています。
トラブルが起きやすい条項と具体的な対策
ITエンジニアがシステム開発契約でトラブルに遭遇するケースの多くは、特定の条項の解釈が発注者との間でズレることで発生します。
ここからは、特に注意が必要な条項について参考条項交えてご紹介します。
納期・工期に関する条項
トラブル事例
- 発注者側の確認遅延により納期に遅れが生じたが、納期延長を認めてもらえない
- 仕様変更を追加的に求められ工期が圧迫されたが、最終納期はずらせないと言われた
システム開発の現場では、納期遅延は深刻なトラブルに発展します。
特に、発注者側都合による遅延や、予期せぬ技術的な課題が発生し、当初の計画通りに進まないケースが多く見られます。
契約書での対策
- 本開発の作業工程及び納期は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 要件定義フェーズ
期間:契約締結日から◯週間
成果物:要件定義書
(2) 基本設計フェーズ
(3) 詳細設計フェーズ
(4) 開発フェーズ
(5) 総合テストフェーズ - 各フェーズの開始時期は、前フェーズの完了を前提とする。
- 本条に定める納期は、第○条(発注者の確認)に定める発注者の確認期間を含まないものとする。
- 発注者は、受注者から成果物の提出を受けた場合、以下の各号に定める期間内に確認を行い、その結果を受注者に通知するものとする。
(1) 要件定義書:◯営業日以内
(2) 基本設計書:◯営業日以内
(3) 詳細設計書:◯営業日以内
(4) テスト結果報告書:◯営業日以内 - 発注者は、前項の確認の結果、修正が必要と判断した場合、修正箇所及び理由を具体的に明示して受注者に通知するものとする。
- 発注者が第1項に定める期間内に確認結果を通知しない場合、当該成果物は承認されたものとみなす。
- 発注者の確認期間が第1項に定める期間を超過した場合、超過日数分だけ最終納期を延長するものとする。
- 発注者は、本開発の実施期間中において、書面により仕様の変更を要請することができる。
- 受注者は、前項の要請を受けた場合、以下の各号に定める事項を検討し、その結果を発注者に通知するものとする。
(1) 仕様変更の実現可否
(2) 追加工数の見積もり
(3) 納期への影響 - 仕様変更に伴う工期の変更は、以下の基準に従うものとする。
(1) 追加工数が5日未満の場合:現行の工期を維持
(2) 追加工数が5日以上20日未満の場合:工期を2週間延長
(3) 追加工数が20日以上の場合:両者協議の上、工期を決定 - 発注者は、前項の工期変更に同意した場合に限り、仕様変更を実施することができる。
検収基準に関する条項
トラブル事例
- 検収基準が曖昧で、主観的な判断により検収が通らない
- テスト基準が明確でなく、際限のない修正要求が続く
- 性能要件やセキュリティ要件の解釈を巡って見解の相違が発生
検収に関するトラブルは、報酬支払いに直接影響するため、特に注意が必要です。
特に非機能要件の検収基準が曖昧な場合はプロジェクト終盤で大きな問題となることがあります。
契約書での対策
- 本開発の検収基準は、以下の各号に定める要件の全てを満たすことをもって合格とする。
(1) ユーザー管理機能
・ID/パスワードによるログインが正常に動作すること
・パスワードは8文字以上で英数字を含むこと
・パスワードリセット機能が正常に動作すること
・メールアドレス変更が正常に動作すること
(2) 商品管理機能
(3) 決済機能 - 各機能の正常動作とは、以下の条件を満たす状態をいう。
(1) エラーメッセージが表示されないこと
- 検収テストは、以下の環境で実施するものとする。
(1) サーバー環境
・OS:
・CPU:4コア以上
・メモリ:16GB以上
・ストレージ:SSD 256GB以上
(2) クライアント環境
・Windows11
・Google Chrome最新版
・Firefox最新版 - 検証方法は以下のとおりとする。
(1) 機能テスト
(2) 負荷テスト
(3) セキュリティテスト - 発注者は、検証に必要なテストデータを受注者に提供するものとする。
- 発注者は、検収テストの結果、不合格と判断した場合、以下の各号に定める事項を具体的に明示して受注者に通知するものとする。
(1) 不合格となった機能
(2) 期待される動作
(3) 実際の動作
(4) 再現手順 - 受注者は、前項の通知を受けた場合、以下の期限内に修正を行い、再検収を受けるものとする。
(1) 重大な不具合(システムが機能停止する等):◯営業日以内
(2) 軽微な不具合(表示崩れ等):◯営業日以内 - 再検収は2回までとし、2回目の再検収後もなお不合格となった場合、発注者は以下の選択肢から対応を選択できるものとする。
(1) 追加の期間と費用を定めて修正を継続する
(2) 不具合の部分を除外して検収を完了する
(3) 本契約を解除する - 再検収に要する期間は、第○条(納期)に定める期間に含まないものとする。
契約不適合責任に関する条項
トラブル事例
- リリースから1年後にバグが発見され、無料で対応を迫られた
- セキュリティの脆弱性が発見され、想定外の追加対応を求められた
- 運用開始後に、大規模な改修を要求された
契約不適合責任は、民法改正により従来の瑕疵担保責任から変更された概念です。
特にシステム開発では、引き渡し後に様々な問題が発見される可能性があり、その対応範囲を明確にしておくことが重要です。


契約書での対策
- 本契約における契約不適合とは、以下の各号に定める状態をいう。
(1) 要件定義書に記載された機能が正常に動作しない状態
(2) 1リクエストあたりのレスポンスタイムが◯秒を超える状態
(3) 同時接続ユーザー数◯名での稼働時にエラー率が◯%を超える状態 - 前項各号に定める以外の不具合であっても、一般的なシステム開発の技術水準に照らして明らかに不適切と認められる状態については、契約不適合とみなす。
- 発注者は、本成果物の検収完了後1年以内に限り、受注者に対して契約不適合の通知を行うことができる。
- 受注者は、前項の通知を受けた場合、以下の各号に定める期限内に対応を行うものとする。
(1) システムの稼働に重大な影響を与える不具合
初期対応:◯時間以内
恒久対応:◯営業日以内
(2) システムの一部機能に影響を与える不具合
初期対応:◯営業日以内
恒久対応:◯営業日以内
(3) 軽微な不具合
対応:◯営業日以内 - 前項の期限内に対応が完了しない場合、受注者は発注者に対して対応状況及び完了見込み時期を電磁的方式により報告しなければならない。
- 受注者は、以下の各号に該当する契約不適合について、無償で修補を行うものとする。
(1) 要件定義書に記載された機能の実装に関する不具合
(2) システムの基本的な動作に影響を与えるバグ
(3) 重大なセキュリティ脆弱性 - 以下の各号に該当する修補については、別途有償対応とする。
(1) 要件定義書に記載のない機能の追加または変更
(2) 発注者の運用環境に起因する問題への対応
(3) 発注者の要望による機能改善 - 前項の有償対応の費用は、作業工数に応じて算出するものとし、その単価は本契約の開発単価を準用する。
- 以下の各号に該当する場合、受注者は契約不適合責任を負わないものとする。
(1) 発注者が提供した仕様、データ、または材料に起因する不具合
(2) 発注者または第三者が本成果物に改変を加えたことによる不具合
(3) 発注者の運用環境(ハードウェア、OS等)に起因する不具合
(4) 要件定義書に記載された動作環境以外での利用に起因する不具合
(5) 通常予見し得ない使用方法に起因する不具合 - 天災地変その他の不可抗力により生じた不具合については、受注者は責任を負わないものとする。
報酬に関する条項
トラブル事例
- 検収遅延により報酬の支払いが大幅に遅れた
- 追加開発の費用算定基準が不明確で、適正な報酬がもらえなかった
- 中途解約時の報酬計算方法を巡ってトラブルに
フリーのITエンジニアにとって、報酬の支払い条件は死活問題です。
特にプロジェクトが長期間に及ぶ場合はなおさら重要です。
きっちり報酬を回収できるように契約条項を確認しておきましょう。
契約書での対策
- 本開発の報酬額は、金○○○万円(消費税別)とする。
- 前項の報酬は、以下の各号に定める時期に、当該各号に定める金額を支払うものとする。
(1) 契約締結時:報酬総額の○%
(2) 基本設計完了時:報酬総額の○%
(3) 検収完了時:報酬総額の○% - 支払方法は以下のとおりとする。
(1) 受注者は、前項各号の時期において請求書を発行する
(2) 発注者は、請求書受領月の翌月末日までに、受注者の指定する銀行口座に振り込むものとする
(3) 振込手数料は発注者の負担とする - 発注者が前項の支払を遅延した場合、年○)%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
- 発注者は、書面により追加開発を依頼することができる。
- 追加開発に関する料金は、以下の各号に定める基準により算定する。
(1) 開発工数1人あたりの単価:金○円(消費税別)
(2) 1人日は○時間として計算する
(3) 休日または営業時間外(平日9:00-18:00以外)の作業については、上記単価の○%増しとする - 追加開発の着手は、発注者が前項の見積書を承認した後とする。
- 追加開発に関する報酬は、当該追加開発の完了確認後、◯か月以内に支払うものとする。
受注者の責めに帰すべき事由による解約の場合、前各項の規定は適用せず、別途協議により精算方法を定めるものとする。
発注者は、30日前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。
前項の解約がなされた場合、以下の各号に従って精算を行う。
(1) 既に完了している工程に対応する報酬は、第○条に定める割合に従って支払う
本条に基づく精算金は、解約日から◯日以内に支払うものとする。
まとめ
今回は、フリーランスのITエンジニアやシステム開発会社の担当者に向けて、システム開発契約における「請負契約」と「準委任契約」の違い、そして契約書作成時の重要条項について解説しました。
- プロジェクトの特性を十分に理解し、適切な契約形態を選択する
- 具体的な数値を含めた明確な契約条項を設定する
- 想定されるリスクに対する対応方法を事前に規定する
クライアントと長期的かつ良好な関係性を築いていくためには、適切な契約形態の選択と重要条項の作成が不可欠です。
また昨今は、AIを活用したシステム開発に力を入れる企業が急増しています。
クライアントから急な依頼があったときに備えて、リスクを抑えた適切な業務委託契約書を用意しておきましょう。
(AI)システム開発契約書の作成はお任せください
| 対応可否 | オーダーメイド作成 | ひな型 |
|---|---|---|
| 事前無料相談 | ◯ | ◯ |
| 料金 | 55,000円~ | 8,099円~ |
| 納期 | 3営業日 | 即時ダウンロード |
| 修正回数 | 無制限 | お客様にて修正 |
| アフターフォロー | 納品後から30日間は無料 | 有料 |
弊所は、(AI)システム開発契約書の作成を得意としております。
- クライアントからシステム開発の依頼がきたので契約書が必要だ
- ネットでシステム開発契約書の作成を探したが適当なものが見つからない
- なんとなく自分でシステム開発契約書を作成してみたが専門家にリーガルチェックしてもらいたい
この様なことでお困りのシステム開発会社様やフリーランスのITエンジニア様は、今すぐ弊所にご相談ください。
しっかりとヒアリングをおこなったうえで、質の高い契約書を作成します。
ネットで拾えるようなペラペラなものではなく、貴社オリジナルの契約書です。
高品質な契約書を用いて、ビジネスを安全かつ効率的に進めましょう。
LINEで簡単!全国どこからでも対応致します。
最初だけ、メールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は電話でお伺いします。
北海道, 札幌,青森, 岩手, 秋田, 宮城, 山形,福島, 東京(東京都23区,千代田区,中央区,港区,世田谷区,大田区,目黒区,品川区,渋谷区,杉並区,中野区,練馬区,新宿区,江東区,墨田区,葛飾区,江戸川区,台東区,文京区,荒川区,足立区,北区,豊島区,板橋区), 神奈川, , 横浜,埼玉県, 千葉, 茨城, 群馬, 栃木, 愛知, , 名古屋,静岡, 三重, 岐阜, 新潟, 長野, 山梨, 石川, 富山, 福井, 大阪, 京都, 奈良, 兵庫, ,神戸滋賀, 和歌山, 岡山, 広島, 鳥取, 山口, 島根, 愛媛, 徳島, 高知, 香川, 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島, 沖縄
商取引に関する契約書
- 動産売買契約書
- 土地売買契約書
- 土地建物売買契約書
- 継続的売買契約書
- フランチャイズ契約書
- 特約店契約書
- OEM契約書
- 販売代理店契約書
- 秘密保持契約書(NDA)
- 事業譲渡契約書
- 企業主導型保育従業員枠共同利用契約書
- M&Aアドバイザリー契約書
- 継続的商品売買契約書
- スポンサー契約書
- 営業代行委託契約書
- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)
- タクシーデジタル広告掲出契約書(約款)
- YouTubeチャンネル共同運営契約書
- ドローン関連サービス委託契約書
- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書
賃借に関する契約書
- 建物使用貸借契約書
- 建物賃貸借契約書
- 定期建物賃貸借契約書
- 定期借地権設定契約書
- 事業用定期建物賃貸借契約書
- 駐車場賃借権契約書
- 社宅借り上げ契約書
賃金と担保に関する契約書
- 債権譲渡契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 抵当権設定契約書
- 代物弁済契約書
- 準消費貸借契約書
- 集合動産譲渡担保契約書
- 質権設定契約書
請負・業務委託契約書
- 業務委託契約書
- 建設工事請負契約書
- 不動産管理委託契約書
- コンサルタント契約書
- AIシステム開発契約書
- WEBサイト制作業務委託契約書
- 営業委託契約書
- ヘアーサロン美容師業務委託契約書
- ヘッドスパ・セラピスト業務委託契約書
- ネイリスト業務委託契約書
- アイリスト業務委託契約書
- ヘアサロン・美容室面貸し契約書
- ヨガ・ダンス教室業務委託契約書
- 給食提供業務委託契約書
- 訪問歯科医療委託契約書
- 動画制作業務委託契約書
- 声優・ナレーター動画出演委託契約書
- ライター業務委託契約書
- 脚本(シナリオ)執筆委託契約書
- SNS運用代行契約書
- 動画・舞台出演契約書
- コールセンター業務委託契約書
- システム・機械保守メンテナンス契約書
- セミナー・講演会・出演契約書
- イラスト制作業務委託契約書
- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
- ダンス・舞踊創作の委託契約書
- デリヘル店業務委託契約書
- マッサージ、リラクゼーションサロン業務委託契約書
- レンタル彼女キャスト業務委託契約書
- オンライン事務(バックオフィス)代行サービス業務委託契約書
- 社員研修講師委託契約書
- 研修の外部講師との業務委託契約書
- 音楽教室の講師業務委託契約書
- 料理教室の講師業務委託契約書
- 学習塾講師業務委託契約書
- アートメイク看護師業務委託契約書
- 医療ハイフ看護師業務委託契約書
- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
- 住宅リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書
- 民泊施設清掃委託契約書
- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書
- 幼稚園・保育園・児童クラブとスポーツインストラクターの業務委託契約書
- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士との業務委託契約書
- 校正・校閲スタッフ業務委託契約書
- 管理栄養士との業務委託契約書
- PC・プログラミング講師業務委託契約書
- インテリアコーディネーター業務委託契約書
- 在宅コールセンター業務委託契約書
- ポスティング業務委託契約書
労働に関する契約書
- 雇用契約書
- 労働者派遣基本契約書
- 入社・退社誓約書
- 身元保証契約書
- 出向契約書
- 専属マネジメント契約書
著作権に関する契約書
- 著作権譲渡契約書
- 著作権利用許諾契約書
- キャラクター商品化権許諾契約書
家族・近隣に関する契約書
- 贈与契約書
- 遺産分割協議書
- 夫婦財産契約書
- 任意後見契約公正証書
- 通行地役権設定契約書
- ヘッドスパサロンとセラピストの業務委託契約書
- 美容院サロンとスタイリストの業務委託契約書
- 美容院サロンの面貸し契約書
- まつエクサロンとアイリストの業務委託契約書
- ネイルサロンとネイリストの業務委託契約書
- マッサージサロンとセラピストの業務委託契約書
- レンタル彼女事業者とキャストの業務委託契約書
- SNS運用代行委託契約書
- イラスト・ロゴ制作の業務委託契約書
- 動画・映像制作の業務委託契約書
- ライター・記事執筆業務委託契約書
- 写真家・フォトグラファー業務委託契約書
- 社員研修の委託契約書
- 外部講師との研修業務委託契約書
- セミナー・講演会出演委託契約書
- デリヘル店女の子業務委託契約書
- 従業員退職後のSNS削除要請に関する同意書
- 音楽教室講師業務委託契約書
- 料理教室講師業務委託契約書
- 学習塾講師業務委託契約書
- オンライン事務(バックオフィス)業務委託契約書
- 営業代行委託契約書
- フルコミ不動産エージェントとの業務委託契約書
- デジタルサイネージ広告掲出契約書(約款)
- アートメイク看護師業務委託契約書
- ヨガ・ピラティスインストラクター業務委託契約書
- スポーツインストラクターの業務委託契約書(対幼稚園・児童クラブ)
- リフォーム会社と外注の職人との業務委託契約書
- [M&A]飲食店の事業譲渡契約書(法人から→法人へ)
- (AI)システム開発委託契約書
- 民泊施設清掃委託契約書
- 訪問型PC/ITサポートの技術スタッフとの業務委託契約書
- オンライン心理カウンセラー・臨床心理士の業務委託契約書
- 校正・校閲業務委託契約書
- 管理栄養士との業務委託契約書
- PCプログラミング講師との業務委託契約書
- インテリアコーディネーター業務委託契約書
- 在宅コールセンター業務委託契約書
- ポスティング業務委託契約書
- 治療院、接骨院、エステサロン等のパッケージライセンス契約書